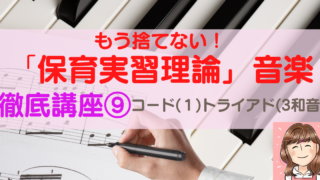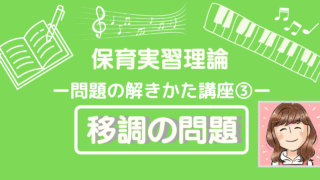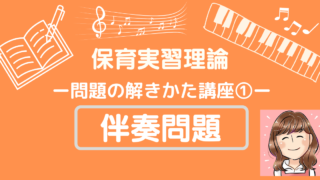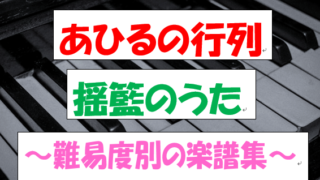ようやく筆記試験に合格すると、
いよいよ実技試験ですね。
「造形」は当日に課題が出されるので、
あらかじめ出題される
「言語」「音楽」を選択する人が
多いのではないでしょうか?
でも・・・
「試験官の前で歌ったり楽器を弾くなんて、
緊張しそうでコワイ」
「ピアノを触るのが久しぶりで、間に合う?」
そんなアタナに、
実はとっておきの「合格のコツ」があるんです。
長年にわたって
保育士養成校でピアノ実技を指導し、
自分自身も国家試験を受験して合格した私が、
そのコツをもれなく伝授します!
合格のコツ①~③を読んで実践することで、
ピッタリの譜面をゲットできます
・歌いながら弾くことに自信が持てます
・試験当日を余裕の気持ちで
迎えることが出来ます
まず、この記事「コツ①」では、
練習に入る前の大前提の3つをご紹介します!
大前提 その1)歌をしっかり歌う!!
まず、大前提の中の大前提です。
それは・・・ずばり!
歌をしっかり歌うこと!!
意外でしたか~?
ここが一番のポイントになります。
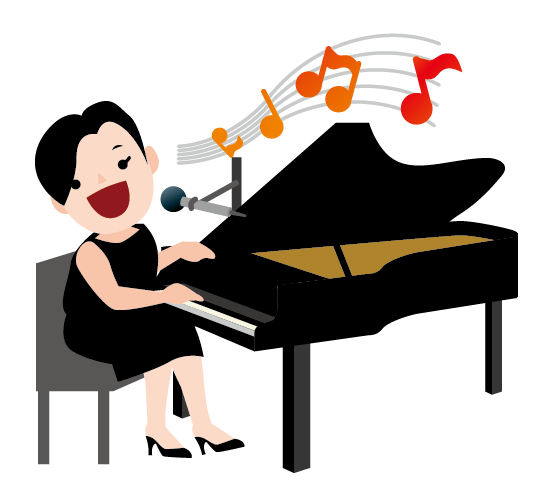
しっかり歌おう!!
昔ピアノを習っていた人、
または急いでピアノ教室に習いに行く人、
そんな人たちが陥りがちなのが・・・
「ピアノを上手に弾く」ことに集中してしまい、
「歌がテキトー」になってしまうことです。
世のピアノの先生たちも、
「ピアノを上手に弾くこと」だけを教えてくれます。
でも、
あくまで「保育士試験」なので、
「保育の現場で通用すること」が
大事なのです。
「ピアノの演奏試験」ではないのです。
つまり・・・
ピアノが弾ける人も
「多少、難易度を下げる」ことも考える
■子どもたちが保育士の歌を聴いて
「耳で」覚えることを意識して、
「歌詞」をハッキリ歌う。
■子どもたちと一緒に歌うことをイメージして、
前奏から歌に入るとき
「さんはい!」とか「どうぞ!」などと
声掛けする。
この3点が、非常に大切なポイントです。

えっ??
ピアノは簡単でよいの?
難しい楽譜で弾いた方が、
点数が高いのでは・・・?

もちろん、
ピアノ演奏に長けた人は、
難しいアレンジで良いですよ!
でも、ピアノが心配な人は、
ぜひピアノ部分を
あえて簡単バージョンにして、
その分、
歌を堂々と歌うのがおススメです!
というわけで、
これからお伝えしていく練習も、
まずは歌から始めるんですよ!
大前提 その2)速すぎない、遅すぎない
曲に適したテンポ、
子どもが歌いやすいテンポで演奏するのは、
最低条件です。
よく、慣れてくると速く弾く人、
速く弾く方が「上手に聞こえる」と
思っている人がいますが・・・
次のことを考えてみましょう。
- この曲に合っている速さか?
- 子どもたちがついてこられる速さか?
緊張していても、
落ち着いた速さで弾くことが合格のポイントです!
大前提 その3)表情豊かに
コロナ禍で、
マスクを着けながらの今は難しいですが・・・
「演奏試験」とはいえ、
試験官はあなたの「表情」「態度」も見ています。
だって「保育士試験」なのですから・・・。
いくらスラスラ上手に弾けたとしても、
難しい表情をしていたり、
横柄な態度をとると・・・
全体としての評価が
下がってしまうかも知れません。
そこで・・・
- マスクをしていても
「表情豊かに」を意識する - 演奏前後に「宜しくお願いします」
「ありがとうございました」の挨拶を
気持ちよくする
つまり、目の前に
「一緒に歌う子どもたちがいる」とイメージできる」かが
ポイントです。
以上の3つは、大前提のポイントです
では、このポイントを押さえるために、
次に必ずやること、それは・・・
↑ ↑ これについては、
コツ②の記事でご紹介しますね。
まとめ
この「コツ①」の記事では、
まず「大前提の3つ」を紹介しました。
- 歌をしっかり歌う
- 速すぎない、遅すぎない
- 表情豊かに
さあ、
そろそろ保育士試験の「音楽」弾き歌いは、
歌が大事ということが、
分かりましたか~?

分かったけど・・・
自分にぴったりの楽譜って、
どういうこと~??
それはズバリ、
「自分の歌いやすい高さ」
「その高さの移調楽譜」です!
については、次の投稿合格のコツ②で
詳しくお伝えしますね!!