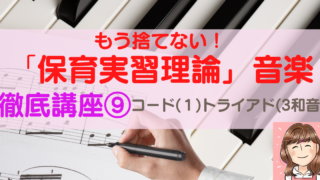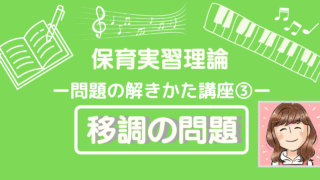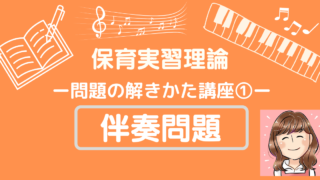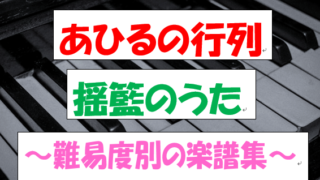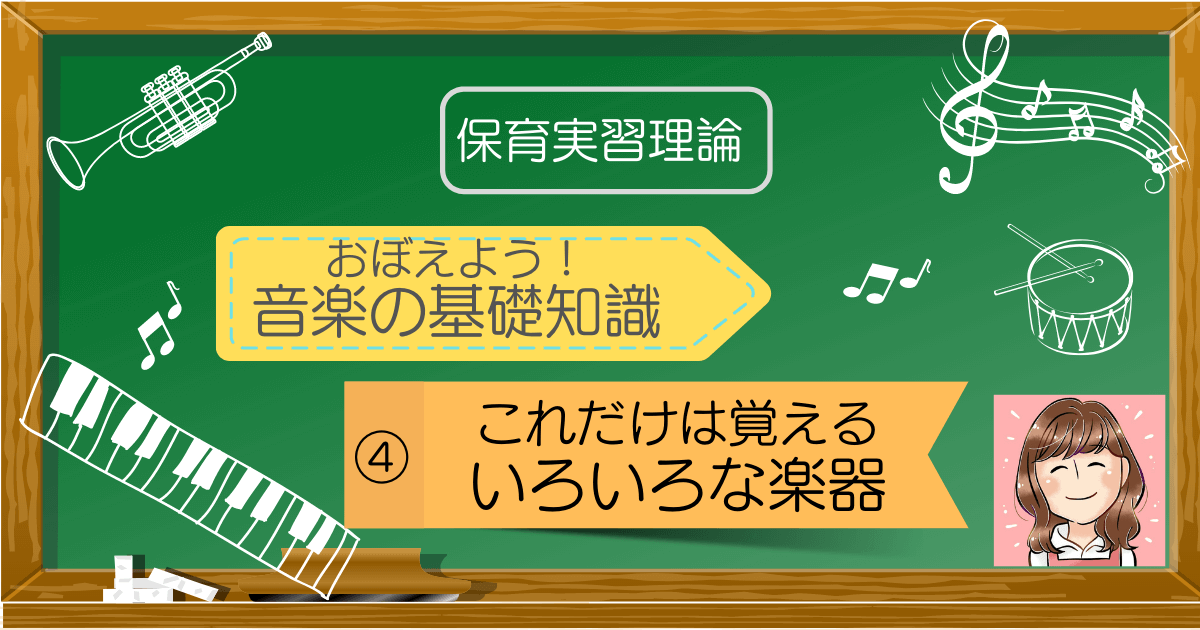問6の選択問題では、
さまざまな音楽の知識が問われますが、
楽器についての出題も多いです。
過去問をすべて見た結果、
3回に2回くらいの割合で、
出ています。
「保育に関係ある?」という楽器も、
出てきていますが・・・
これまで出題された楽器を中心に、
保育士試験に出る可能性が高いものを
まとめていきます。
基礎知識として、
覚えていきましょう。
鍵盤楽器
文字通り、鍵盤がある楽器です。
保育士試験に向けて、
覚えておきたい鍵盤楽器です。
| 名 称 | 覚えておきたい特徴 |
| ピアノ | ・鍵盤は88鍵 ・グランドピアノ、アップライトピアノ ・オーケストラの全ての楽器の音域を 1台でカバーする ・打楽器でもあり、弦楽器でもある ・ハンマーで弦をたたいて音を出す |
| オルガン | ・教会のパイプオルガンが発祥 ・学校の足ぶみオルガン ・鍵盤ごとのパイプやリードに 空気を流して音を出す ➡「管楽器」でもある ・足の鍵盤がある |
| 電子オルガン | ・エレクトーン(YAMAHAの商品名) ・鍵盤を弾いて電気信号を伝えて 音を出す |
| アコーディオン | ・別名「蛇腹楽器」 ・ピアノ式鍵盤、ボタン式鍵盤がある ・鍵盤数は 26鍵・34鍵・37鍵・41鍵が一般的 ・鍵盤数が多いほど重たくなる ・左手ボタンはベース音とコード ボタン数は8~120個とさまざま ・蛇腹を動かして リードに空気をに送って音を出す ・携帯に便利 |
| 鍵盤ハーモニカ | ・金属製のリードに息を吹き込んで 音を出す ・鍵盤数は25~44鍵と 商品によって異なる ※小学校では32鍵が一般的 ・携帯に便利 |
| チェンバロ | ・別名 ハープシコード ・ピアノの祖先 ・ルネサンス音楽、バロック音楽で愛用 ・鍵盤が白と黒、逆 ・弦を爪(プレクトラム)ではじいて、 音を出す ・音が弱く、繊細 |

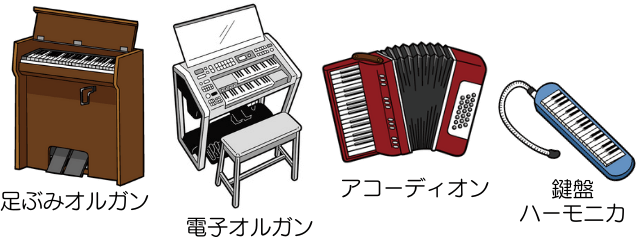
弦楽器
過去問で出されているのは、
ギター、ヴァイオリン、三味線です。
三味線が、
ちょっとビックリですね。
プラスして、
ヴァイオリン属の楽器を、
大きさ順に覚えておくと良いと思います。
| 名 称 | 覚えておきたい特徴 |
| ギター | ・6本(または12本)の弦 ・クラシックギター: ナイロン弦の元祖ギター ・アコースティックギター: スチール弦、フォークギター ・エレクトリックギター: アコギにアンプを取り付けたもの ・どのギターも調弦は同じ 下からミ・ラ・レ・ソ・シ・ミ |
| ヴァイオリン | ・ヴァイオリン属で最も小さく、 最も高音の楽器 ・基本は4弦 ・調弦は下からソ・レ・ラ・ミ ・馬のしっぽを張った弓で音を出す |
| ヴィオラ | ・ヴァイオリン属の 小さいほうから2番目 ・調弦はド・ソ・レ・ラ ・ヴァイオリンより低音 サイズは10cmほど大きい |
| チェロ | ・ヴァイオリン属の 大きいほうから2番目 ・調弦はド・ソ・レ・ラ ・ヴィオラよりさらに低音 大きさは全長125cmくらい |
| コントラバス | ・ヴァイオリン属で最も大きく、 最も低音が出る ・調弦はド・ソ・レ・ラ ・チェロよりさらに低音で、 大きさは全長185cm前後 ・唯一、立って演奏する |
| 三味線 | ・日本の弦鳴楽器 ・3本の弦をバチで鳴らす ・調弦方法は3種類 「本調子」「二上り」「三下り」 ・伴奏する音楽に合わせて 細棹・中棹・太棹に大別される |
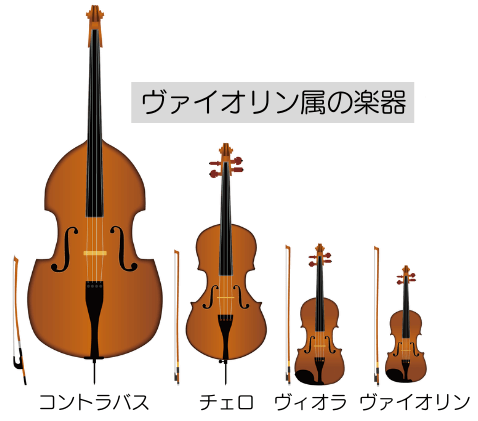
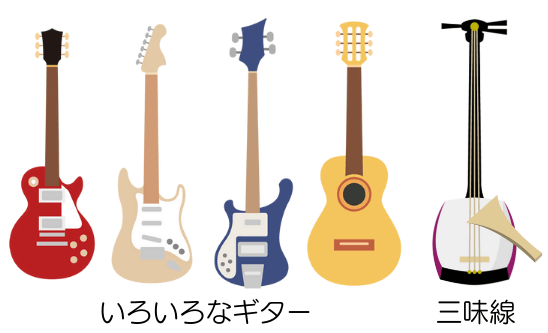
管楽器
管楽器は
「木管」と「金管」に分類されます。
古くは楽器の材質で分かれていましたが、
今では「音の鳴らしかた」で分けられています。
①くちびるの振動で鳴らす
➡金管楽器
②上記以外の鳴らしかた
➡木管楽器
金管楽器
金管楽器は、
問題に出てきたことはありません。
しかし、
木管楽器は出題されているので、
今後、金管も出る可能性アリです。
代表的なものだけ覚えておくと
良いでしょう。
| 名 称 | 覚えておきたい特徴 |
| トランペット | ・金管楽器の中で最高音域をもつ ・くちびるを振動させ、 マウスピースを通して音を出す ・3つのピストンで音を変える |
| トロンボーン | ・スライドという伸縮管で 音程を変える ・くちびるの振動によっても 音の高さを変えられる ・スライドの長さは 約150cm |
| ホルン | ・長い管をぐるぐる丸めた形 ・ベルの直径は約30cm ・マウスピースはろうと型 ・やわらかい音で、 木管楽器とよく調和する |
| チューバ | ・金管楽器では最も大きく、 最低音域を担当 ・音程を変えるバルブは、 タイプにより3~7本 ・重量10~15kg、 長さは80cm前後 |
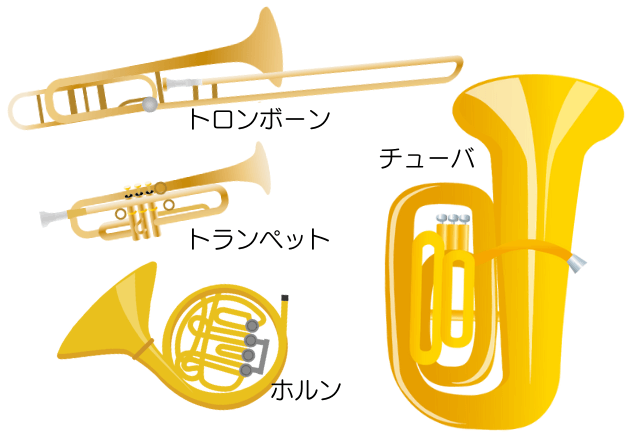
木管楽器
一見すると「金属」で出来ているので
「金管かな?」と思う楽器も、
「木管楽器」です。
令和3年後期の問題で、
「サクソフォーンは木管楽器である」
〇か✕か・・・が問われました。
どちらかというと、
音が高い楽器が木管です。
また、リードを使う楽器が多いです。
| 名 称 | 覚えておきたい特徴 |
| ピッコロ | ・フルートの派生楽器 ・フルートの1オクターブ 高い音が出る ・オーケストラで最高音域 |
| フルート | ・リードを使わない横笛 ・トーンホールを開閉して 音高を変える ・オケではメロディが多い |
| オーボエ | ・2枚のリード「ダブルリード」 ・人の声に近い目立つ音 ・チャルメラが原型 ・最も演奏が難しい楽器として ギネスに登録 |
| クラリネット | ・シングルリード ・4オクターブの音域 (管楽器の中で最も広い音域) ・グラナディラという木材 ならではの柔らかい音色 |
| サクソフォーン | ・一般的には真鍮で作られている ・通称サックス ・木管楽器の中では大音量が可能 ・ジャズやポップスなど 幅広いジャンルで活躍 |
| リコーダー | ・木管楽器の一種 ・プラスチック製のものは 小学校などで使われている ・簡単に音が出せる ・長さの違いにより、音程の異なる いくつかの種類がある |
| オカリナ | ・リードがないエアリード式 ・指穴の数、場所に決まりがない ・さまざまな材質 (陶器製が多い) ・歌口の造りがリコーダーと似ている |
| ハーモニカ | ・リード楽器 ・並んだ穴から息を吸ったり 吐いたりしてリードを振動させる ・高級なものは木製、 教育用はプラスチック製 |
リコーダーやオカリナも、
木管楽器の一種なのです。
覚えておいて損はなさそうですね!
ハーモニカの過去問は、
「ハーモニカはリード楽器である」
〇か✕か、でした。


打楽器
打楽器は、
保育にも取り入れる楽器が多いため、
何回も、何種類も出題されています。
なじみのある楽器でも、
あらためて質問されると
「?」となるケースもあるので、
特徴はしっかり押さえておきましょう!
| 名 称 | 覚えておきたい特徴 |
| マリンバ | ・木琴の一種で 鍵盤打楽器 ・ピアノと同じ配列の 木製の音板が並ぶ ・マレットというバチで たたいて音を出す |
| ハンドベル | ・17世紀イギリスの教会で誕生 ・1つのベルが1つの音を奏でる ・本来は音高によって サイズが異なる ・昭和57年、日本で教育用に 作られたのが「ミュージックベル」 ➡「ハンドベル」とも呼んでいる ➡ミュージックベルは 全て同じサイズ |
| タンバリン | ・浅い小型の太鼓 ・鈴がないもの、皮を張って いないものもある。 ・手や指でたたく他に、 振って鳴らす、フチをこする、 スティックでたたくなど、 いろいろな奏法がある |
| カスタネット | ・スペインの民族楽器 ・スペイン舞踊のフラメンコに 使われる ・一般的には木製、子ども用や 教育用にプラスチック製も ・より速いリズム用に 柄付きカスタネットもある |
| トライアングル | ・金属製 ・金属製の棒(ビーター)で たたいて音を出す ・異なる大きさがあるが、 一定の音律はない ・三角形の形状から 名づけられている |
| マラカス | ・シェイカーの一種 ・木製、プラスチック製など多種 ・中身は木の実、ビーズ、砂利など ・マンボやサルサなど、 ラテン音楽で使われる |
| クラベス | ・2本の木片を 上下にたたいて音を出す ※日本の拍子木は、 平行にたたく ・円柱、または四角柱 |
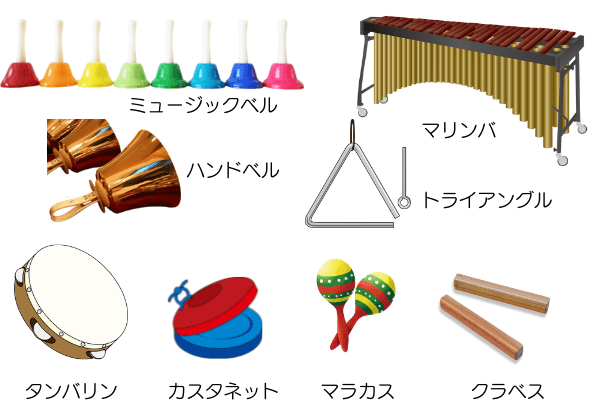
まとめ
保育実習理論の問6で、
楽器についての〇✕は、
・楽器の分類
・発祥の国
・特徴
について問われることが多いです。
なかでも、楽器の分類がダントツで、
〇〇〇の楽器は「打楽器である」
△△△の楽器は「木管楽器である」
という問いが最多です。
今回まとめた5つの分類
①鍵盤楽器
②弦楽器
③金管楽器
④木管楽器
⑤打楽器
は、必ず覚えましょう。
また、楽器の特徴は、
・音の高低
・サイズ
・生まれた国
・どうやって音が出るか
以上について、
ポイントを押さえておくことを
オススメします!